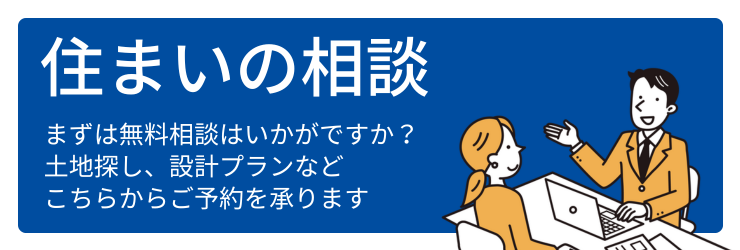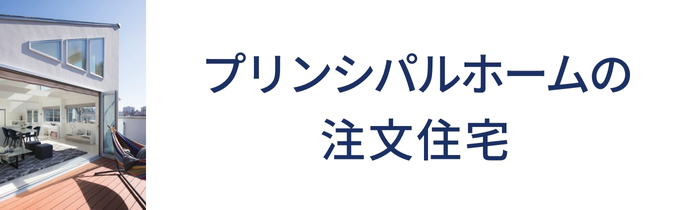「犬走り」という言葉を耳にしたことはありますか? 一般の方にはあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、建築や外構においてはよく使われる用語です。
住宅の周囲に見られる、建物の基礎から少し離れた場所に設けられた細長いスペースを指し、その名の通り「犬が走れるくらいの幅」が語源とされています。
この記事では、犬走りの具体的な機能やメリット、そして設置する際の注意点について素材別に詳しく解説していきます。
犬走りとは? その定義と基本的な機能
犬走りとは、建物の基礎周辺に設けられる、幅30cm〜60cm程度の細長い通路のようなスペースを指します。多くの場合、コンクリートや玉砂利、レンガなどで舗装されており、住宅の外周をぐるりと囲むように設置されます。
主な機能としては、以下のような点が挙げられます。
- 雨水対策: 建物から落ちる雨水が直接基礎に当たるのを防ぎます。これにより、基礎の劣化や土の跳ね返りによる外壁の汚れを防ぎ、建物の寿命を延ばす効果があります。
- 湿気対策: 基礎周りの土壌が常に湿った状態になるのを防ぎ、床下の湿気対策にも貢献します。湿気は木材の腐食やシロアリの発生原因となるため、これを防ぐことは建物の耐久性を高める上で非常に重要です。
- 防犯対策: 犬走り部分に砂利を敷き詰めることで、歩くと音が鳴るため、不審者の侵入を察知しやすくなります。防犯砂利は特に効果的です。
- 美観の向上: 建物と庭の境界を明確にし、建物の足元を引き締める効果があります。様々な素材を用いることで、外観デザインのアクセントにもなります。
- メンテナンス性の向上: 建物の周囲にスペースがあることで、外壁の点検や修繕、配管のメンテナンスなどが容易になります。
このように、犬走りは単なる通路ではなく、建物を様々な外部要因から守り、その美しさと機能性を保つために不可欠な存在と言えるでしょう。
犬走りの素材と施工方法による違い
犬走りの素材には、様々な種類があります。それぞれに特徴があり、費用やメンテナンス性、見た目の印象が異なります。
- コンクリート製犬走り: 最も一般的で耐久性に優れています。施工が比較的容易で、雑草が生えにくいためメンテナンスも楽です。表面を刷毛引き仕上げにすることで滑りにくくしたり、色付けすることでデザイン性を高めることも可能です。費用を抑えたい場合や、機能性を重視する場合には最適な選択肢と言えるでしょう。
- 玉砂利(じゃり)製犬走り: 和風、洋風問わず様々な住宅にマッチし、自然な雰囲気を演出します。歩くと音が鳴るため、防犯効果も期待できます。ただし、玉砂利の下に防草シートを敷かないと雑草が生えやすく、砂利が散らばりやすいというデメリットもあります。定期的な補充や均し作業が必要になることもあります。
- レンガ・タイル製犬走り: デザイン性が高く、建物の外観をより魅力的に演出します。耐久性も高く、色やサイズのバリエーションも豊富なため、オリジナルのデザインを楽しむことができます。ただし、コンクリートや玉砂利に比べて費用が高くなる傾向があり、目地の清掃が必要になる場合もあります。
- インターロッキングブロック製犬走り: 様々な色や形状のブロックを組み合わせてデザインできるため、オリジナリティの高い犬走りを実現できます。透水性のあるタイプを選べば、水たまりができにくく、雨水浸透にも貢献します。レンガやタイルと同様に費用は高めですが、メンテナンス性は比較的良好です。
- 枕木風犬走り: 木材のような温かみのある雰囲気を演出したい場合に適しています。コンクリート製の枕木風素材や、樹脂製の擬木など、耐久性の高い素材を選ぶと良いでしょう。本物の木材を使用する場合は、防腐処理が必要となり、定期的なメンテナンスが不可欠です。
これらの素材は単独で使うだけでなく、複数を組み合わせてデザインすることも可能です。例えば、コンクリートの犬走りの一部に玉砂利を敷いたり、レンガで縁取りをしたりするなど、工夫次第で多様な表情を生み出すことができます。
▶比較検討にプリンシパルホームの注文住宅のカタログを是非ご覧ください。【7冊まで無料】
犬走りとは? 設置のメリットと注意点
犬走りを設置することには、多くのメリットがあります。しかし、いくつか注意すべき点も存在します。
犬走りのメリット
- 建物の保護: 前述の通り、雨水や湿気から基礎や外壁を守り、建物の劣化を防ぎます。特に日本の高温多湿な気候においては、基礎の湿気対策は非常に重要です。
- シロアリ対策: 基礎周りの湿気を減らすことで、シロアリの発生リスクを低減できます。シロアリは湿った木材を好むため、乾燥した環境を保つことが予防につながります。
- 雑草対策: 犬走りをコンクリートなどで舗装することで、建物の基礎周りに雑草が生えるのを防ぎます。これにより、草むしりの手間を大幅に削減できます。
- 泥はね・砂はね防止: 雨が降った際に、雨水が土に落ちて跳ね返り、外壁や窓を汚すのを防ぎます。これにより、外壁の美観を保ち、清掃の手間を減らすことができます。
- 防犯効果: 砂利敷きの犬走りであれば、歩くと音が鳴るため、不審者の侵入を察知しやすくなります。また、犬走りが通路となることで、敷地への侵入をためらわせる効果も期待できます。
- メンテナンススペースの確保: 建物周りの狭いスペースでも、犬走りがあることで、外壁の点検や補修、配管の確認などの作業がしやすくなります。
犬走りの注意点
- 費用: 犬走りの設置には当然ながら費用がかかります。素材や面積、施工方法によって大きく異なりますが、数十万円から百万円以上になることもあります。新築時に計画に含めるか、リフォームとして行うかによっても費用感が変わってきます。
- 水はけ: 犬走りは水はけを考慮して適切な勾配をつける必要があります。勾配が不十分だと、水たまりができたり、雨水が建物側に流れ込んでしまったりする可能性があります。専門業者に依頼し、適切な排水計画を立てることが重要です。
- メンテナンス: コンクリート製であれば比較的メンテナンスは楽ですが、砂利敷きの場合は定期的な雑草抜きや砂利の補充が必要になります。レンガやタイルの場合は、目地の清掃が必要になることもあります。
- 熱の蓄積: 夏場はコンクリートや舗装材が日差しを吸収し、熱を蓄積することがあります。特に狭い敷地の場合、周囲の温度上昇につながる可能性もあります。通気性の良い素材を選んだり、日陰になるような工夫をしたりすることも検討すると良いでしょう。
- 狭小地の問題: 敷地が狭い場合、犬走りを設けることで通路がさらに狭くなり、生活動線を妨げる可能性があります。その場合は、幅を最小限にする、一部のみ設置するなど、工夫が必要になります。
これらのメリットと注意点を総合的に考慮し、ご自身の住宅やライフスタイルに合った犬走りの計画を立てることが大切です。
▶比較検討にプリンシパルホームの注文住宅のカタログを是非ご覧ください。【7冊まで無料】
犬走りをDIYで作ることはできる?
犬走りの設置は、比較的シンプルな構造であるため、DIYに挑戦する方もいらっしゃいます。しかし、きれいに仕上げるためには専門的な知識が必要です。
出来れば、適切な価格と実績がある外構専門業者、建築会社に依頼するのが良いでしょう。
【今週末開催決定】プリンシパルホーム町田本社・横浜支店で家づくり・土地探し・設計の無料相談!ご来社の際には最新の未公開土地情報もご紹介いたします!
まとめ
犬走りとは、建物の足元を雨水や湿気、雑草、そして不審者から守るための重要なスペースです。単なる通路としてだけでなく、建物の耐久性を高め、美観を向上させ、そして日々のメンテナンスを容易にする多岐にわたる役割を担っています。
コンクリート、玉砂利、レンガ、インターロッキングブロックなど、様々な素材があり、それぞれが異なる特性とメリットを持っています。ご自身の住宅の外観デザインや予算、そしてメンテナンスにかけられる手間などを考慮して、最適な素材と施工方法を選ぶことが大切です。
DIYでの設置も可能ですが、水勾配や地盤固めなど、専門的な知識と技術が必要な部分もあります。完璧な仕上がりや長期的な耐久性を求めるのであれば、信頼できる専門業者に依頼することをおすすめします。
犬走りは、住宅の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するために欠かせない要素です。この記事が、犬走りについての理解を深め、ご自身の住宅における最適な選択の一助となれば幸いです。
関連記事
・狭小住宅に中庭という選択で光と風に満ちた暮らしを手にいれる ・中庭のある家のメリットとデメリット、実例から学ぶ ・おしゃれな家のデザインと外観を魅力的にするポイント
▶比較検討にプリンシパルホームの注文住宅のカタログを是非ご覧ください。【7冊まで無料】